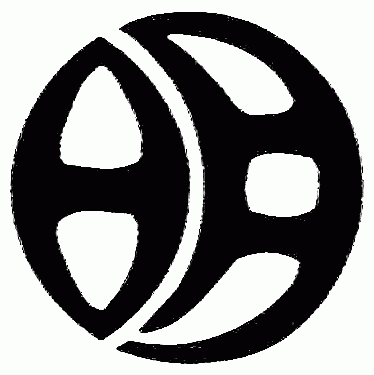8月1日(金)、名古屋大学大学院多元数理科学研究科教授の大平徹先生に「数学と身近な現象 コロナ禍から渋滞まで」というテーマの講座をお願いしました。参加者は44名でした。


数学が世の中でどのように使われているか、4つの例で教えていただきました。
1つ目はコロナの感染予測についてです。SIRモデルを使って感染者数のピークを低くする方法を提言したり、ビッグデータを用いて人々の活動と感染者数には2週間程度のずれが生じることを発見されたりしました。潜伏期間を考慮するための遅れ微分方程式も紹介されました。
2つ目は集団行動についてです。まず、渋滞が起こる仕組みを説明していただきました。「最適速度モデル」に遅れや揺らぎを考慮すると、自然渋滞の発生が観測できました。次に、ひばりや魚などの群れの様子を、数理モデルを構築し、コンピュータグラフィックスによるシミュレーションで再現していただきました。
3つ目は暗号についてです。1960年代に提案された「公開鍵暗号」が1977年に「RSA暗号」として実現され、今も使われていることを教えていただきました。
4つ目は追跡と逃避についてです。単純なルールを複数重ねることで、自然界で行われる動きと同じような動きをすることを見せていただきました。
どの話も本来は難しい内容であると思いますが、かみ砕いて分かりやすく話していただき、数学を身近に感じることができました。