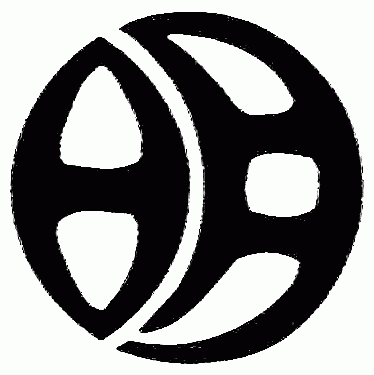夏休みの物理実験室には、MCスプラウト「課題探究自主講座」で実験を行う生徒や、SSH部物理・地学班の班員が多く訪れていました。
連日様々な実験が行われていましたが、その中のいくつかを紹介いたします。
①重力加速度の精密測定に向けた実験
入部したての1年生が実験スキルを身に付けるために始めた単振り子を用いた重力加速度の測定ですが、実験方法に改善を加えながら測定精度の向上に努めています。
今後は、海外の学校にも協力を仰ぎ、様々な場所での実験をして、海外共同研究を実施していく予定です。
一見単純な研究テーマですが、取り組んでいくと奥が深いことがわかり、様々な方法に派生しながら研究を行っています。



②LEDの温度変化による波長の変化の実験
例年明和祭で様々な実験を行っているSSH部ですが、今年度は液体窒素実験の新たなテーマとして、LEDの温度変化による波長の変化の実験を予定しています。
最近インターネット上で話題になったことから、自分たちでもぜひ試してみようと始めた実験ですが、実際に行ってみるとその現象の面白さに魅了されました。
理論的な難しさもさることながら、この面白さを多くの人にわかりやすく伝わる明和祭のサイエンスショーにすることにも難しさがあり、楽しくも試行錯誤しながら実験を繰り返しています。
また、いずれは分光器を用いて波長を測定し、定量的な実験へと深化させることも考えています。

↑オレンジ色のLEDを液体窒素で冷やすと…

↑黄色に変化し、

↑緑に変化します。
③原始惑星系円盤の解析
名古屋大学大学院理学研究科天体物理学研究室の協力のもと、名古屋大学教育学部附属中・高等学校と共同で進めている研究です。
コロナ禍のために対面で活動をすることはほとんどありませんが、Discordを用いた議論や、時にはZoomでのミーティングを行うことで活発に活動が行われています。
最近は、電波望遠鏡からの電波強度のデータから原始惑星系円盤の長半径・短半径を取り出す作業をPythonで行うことに取り組んでおり、コードが完成すれば解析できる天体の数を大幅に増やすことができるため、より説得力のある研究発表ができると考えています。

この他にも、課題探究自主講座・部活動ともに様々な活動が行われた物理実験室ですが、9月以降も更に活発な活動が期待されます。