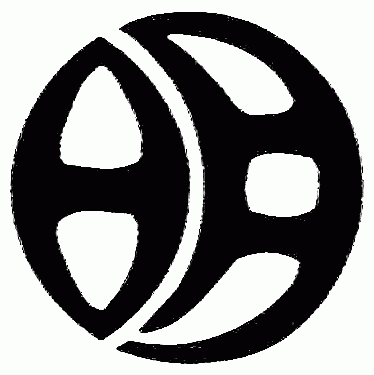6月21日(火)の午後に、学校設定科目「SSH理科探究」の一環として、「SSH理科特別講座」を実施しました。
本企画は、大学の研究者による講義や実習を通して、最先端の研究や技術に触れることにより知的視野を広げるとともに科学技術への興味関心を高め、科学リテラシー、探究力、国際共創力をの育成をすることを目的として、実施しました。
(その成果は、SSH研究開発実施報告書で報告いたします。)
講座1 名古屋大学大学院理学研究科 准教授 立原研悟先生(電波天文学)
「アルマが私たちに教えてくれる宇宙のこと」と題してご講演をいただきました。
星の誕生のメカニズム解明ついての最新研究について、美しい天体画像に魅了されながら紹介していただくことができました。
また、後半の実習では、実際に南米チリに設置されているALMA望遠鏡の観測データの解析を参加生徒1人1人が行い、原始惑星系円盤の中心星の質量を求めました。ALMAで観測されるのは電波だけですが、それを「ケプラーの法則」や「ドップラー効果」といった高校物理で学んだ知識を駆使することで数百万光年先の天体の質量を求めることができることに喜びを覚えるとともに、天体の質量を求めるという研究の奥深さを実感することができたようです。

講座2 名古屋大学工学部 講師 久志本真希先生(電子工学)
青色LEDで有名な窒化物半導体研究の最前線や光デバイスや半導体の基礎、工学部に進学し研究者になるまでの道のりについて、聞くことができました。高度な内容も分かりやすく、テンポ良く説明していただき、また生徒からの質問にも丁寧に答えていただきました。生徒からの質問に答える形でしたが、女性が工学部で学び、研究することについて、メリット・デメリットを経験を踏まえて答えていただきました。工学部を目指す女子生徒には特に参考になったと思います。

講座3 名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(ITbM) 教授 伊丹健一郎先生(物質理学)
合成化学の魅力や異分野融合の重要性をお話いただきました。 ITbMでは世界最高水準の学者が集まり、地球上にある「様々な問題」に対して「スーパー分子で答えを出す」ための研究が行われていること、そして、多くの成果が世界から高い評価を受けていることをお教え頂きました。そして、これから進路決定をする3年生に向けて、”Be unique! Go crazy!” 夢中になれることを見つける方法はないので、毎日毎日、全力で生きて、ひとつでも新しいことに挑戦してみよう!との熱いメッセージとしていただきました。

講座4 名古屋工業大学工学部 教授 柴田哲男先生(生命・物質化学)
「創薬を支える有機化学 サリドマイドのはなし」と題してご講演をいただきました。
サリドマイドは、1960年代に大きな薬害問題となりましたが、現在は多発性骨髄腫、ハンセン病、エイズ等の特効薬として見直されています。
今回はその薬害問題のお話に始まり、ものづくりの工学部として、催奇形性の無い薬を目指した創薬設計の立場からのお話まで、高校生にもわかりやすく、ユーモアも織り交ぜてお話いただきました。質疑の時間には生徒からの多くの疑問に丁寧にお答えいただきました。

講座5 名古屋大学博物館 特任教授 大路樹生先生(古生物学)
「動物の進化:モンゴルのフィールドワークから」と題してご講演をいただきました。
地球と他の惑星とは何が違うのか。生物の多様性と進化はどのようにして起こったのか。「カンブリア爆発」を中心に、生物の進化史と化石研究についてお話しいただきました。また、モンゴルの化石調査で発掘された動物が動き回った後の化石(生痕化石)から分かる、カンブリア前後の動物の生態の変化など、新しい知見も紹介していただきました。先生の発見した新種の生物の話など研究に対する姿勢や、大学での学びの在り方についてもお話しいただきました。