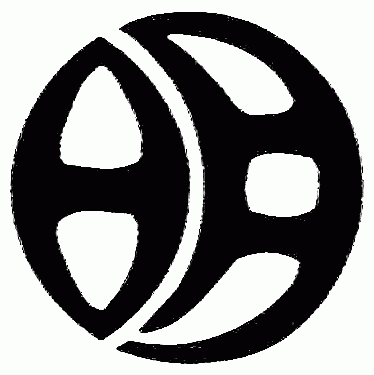6月22日(火)の午後に3年生に対して実施されているSSH理科探究の授業の一環として、SSH理科特別講座を実施しました。
愛知教育学大学教育学部 教授 戸田茂 先生
演題「南極の過去・現在・未来」
高校で学ぶ数学や物理で地震に関する様々な数値を求める事ができる事、また、ばねを使った実験で地震波の特徴を確認し、実際の地震波の記録から地下構造が明らかになる事を教えていただきました。
南極での研究から過去の地球環境が明らかになったり、南極での調査の様子を写真で見せていただき、南極が抱える現在の問題を指摘していただき、これからの地球規模での環境問題を考えるきっかけをいただきました。
南極クイズもあり、みんなで楽しむ事ができました。

名古屋大学大学院情報学研究科複雑系科学専攻 教授 吉田久美 先生
演題「アントシアニンを用いた青色着色料の可能性」
花や野菜、果実、種子などに含まれる植物色素であるアントシアニンは、赤から紫、青色までの幅広く美しい発色を持ちます。まず、この発色とその安定性について、基礎知識を解説していただき、さらに、これをベースとして、アントシアニン系着色料の現状、さらには、青色着色料の実現可能性について説明していただきました。
2年生時の課題研究(理科分野)では、天然物など身近なものや、身近な現象に注目してテーマ設定した研究が多数見られました。このようなテーマに取り組んだ生徒には、振り返りをする良い機会になり、「探究する」ことや「深く追求する」ことの大切さを感じるとともに、「研究に対する気持ちや考え方の変容」を読み取ることができ(事後、評価アンケートの集計結果より)、大変効果的な場面となりました。

名古屋市立大学薬学部 准教授 井上靖道 先生
演題「がん細胞の特徴・がん化学療法」
分子標的薬についての最近の知見を、高校生にもわかりやすく話していただきました。
講義終了後には多くの質問が寄せられました。

自然科学研究機構 基礎生物学研究所 教授 新美輝幸 先生
演題「昆虫の模様と形の多様性を探る」
テントウムシの模様はどう決定されるのか?カブトムシの角の雌雄差はどのような遺伝子によって決定されるのか?様々な環境に適応して進化してきた昆虫たちの多様な形態について、進化的な観点と遺伝的な観点からお話しして頂きました。

南洋理工大学 Assistant Professor 伊藤慎庫 先生
演題「化学を磨いて世界へ飛び出そう」
前半に、伊藤先生の学生生活からこれまでの経緯に沿って、受験勉強の仕方や、大学進学にあたって必要とする志などについて教わりました。その後、生活科学と強く関係するポリマーの例とともに有機化学分野の簡単な講義を受け、南洋理工大学で今まさに取り組まれている、ベンゼン環を基軸とした全く新しい化合物の開発状況とその経緯についてご講義していただきました。
質問タイムを交えつつ、講座の最後には3年生の聴衆へ向けた受験への向き合い方についてもご教示いただき、生徒にとって有意義な時間となりました。